Kampfgruppe Peiper 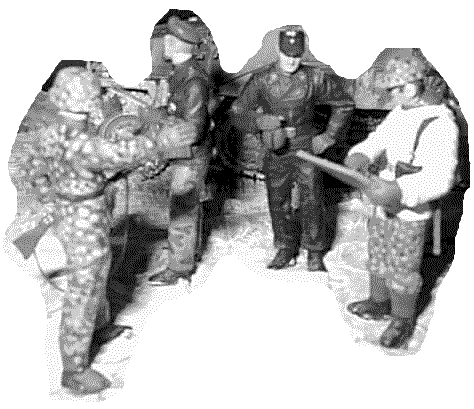
「パイパー戦闘団」イントロダクション
(1)はじめに
このコンテンツで紹介する一連のディオラマは、1944年12月に発動された「ラインの守り」作戦、すなわち「バルジの戦い」にて編成されたヨッヘン・パイパーSS中佐率いるパイパー戦闘団("Kmapfgruppe Peiper" )をテーマにしたものです。なお、ディオラマの紹介は制作順序なので、戦記の順序とは一致していません。
(2)歴史的背景
1944年12月、ヨーロッパでのドイツ第三帝国の敗色は、濃厚なものとなっていた。東部戦線では、ソ連軍は、ソ連領土のほとんどを解放しワルシャワに達していた。西部戦線では、マーケット・ガーデン作戦の頓挫があったものの、連日のドイツ本土へ戦略爆撃は、ドイツの戦争遂行力を著しく低下させ、連合軍はドイツ国境へと達していた。連合軍将兵の多くは、クリスマスまでに戦争は終結すると思っていた。しかし、そのような状況下でもヒトラーは、比較的戦意の低い米英の連合軍へ一大打撃を与えることにより米英と講和し、東のソ連軍へ全力を当たることを考えていた。ドイツ軍は過去アルデンヌ地方を1914年、1940年と突破しその2度とも成功している。そのアルデンヌにて制空権の奪われた状況下の元、連合軍航空機が悪天候で出撃不可能な冬の時期に、戦車部隊を中心にミューズ川を越え、一気にアントワープまで進出し連合軍の戦線を分断し、講和に持ち込もうという作戦である。作戦名は、名称から連合軍を欺くために「ラインの守り作戦」と名付けられた。この作戦のためにドイツ軍は、20万の兵力と残存するほとんどの戦車兵力を投入した。 結果的には、ドイツ軍の補給不足、天候の回復による連合軍空軍の反撃、そして連合軍の圧倒的物量は如何ともしがたく、ドイツ軍は敗北する。この戦いは、南北の部隊(南方の第6戦車軍ではパイパー戦闘団のみが勇名を馳せることになる)の前進が作戦開始直後に行き詰まり、中央の第5戦車軍が突出する形になった。このためこの戦線の形状がバルジ(突出部)に似ていたため、この戦いは、バルジの戦いと呼ばれる。
(3)パイパー戦闘団
パイパー戦闘団は攻撃の主軸の一つである第6戦車軍、SS第I戦車軍団、SS第1戦車師団「ライプシュタンデルテ・アドルフ・ヒトラー(LAH)」を中心に編成され(その他に国防軍第84高射砲大隊、SS第501重戦車大隊などが配属)、5つ予定された前進路のうち前進路Dを進むことになっていた。指揮官は、当時SS第1戦車師団SS第1戦車連隊長であった、ヨッヘン・パイパーSS中佐。
1965年制作のアメリカ映画「バルジ大作戦」(原題”Battle of the Bulge"、監督ケン・アナキン)は、3時間にも及ぶ大作でこのパイパー戦闘団をモデルにしたものです。主演は、ヘンリー・フォンダ(若き日のチャールズ・ブロンソンやテリー・サバラスも出演しています)ですがアメリカ軍の誰をモデルにしたのかは知りません。しかし、ロバート・ショー演じるドイツ軍のへスラー大佐は、紛れもなくパイパーをモデルにしています。
映画では、アメリカ軍のM47パットンが、ドイツ軍のケーニッヒ・ティーガー(?)として使用されています。(アメリカ軍側は、M24チャーフィーをシャーマン(?)としている)おそらく、この映画の影響(その昔、テレビの洋画劇場で何度も放映されていた)でバルジの戦いというと、ドイツ軍のケーニッヒ・ティーガーが大活躍したという印象を植付けられたような気がしますけど、実際は違います。ケーニッヒ・ティーガーはSS第501重戦車大隊所属でパイパー戦闘団にはその一部の20輌が配属されてましたが、部隊の主力は、パンターと4号戦車でした。パイパー自身はケーニッヒ・ティーガーのような図体のでかい戦車は自分の与えられた機動戦の任務では使いようがないと考えていたようで、SS第501重戦車大隊はパイパー戦闘団の後尾についていたようです。したがって、映画のようにケーニッヒ・ティーガーの大部隊が先頭を切って侵攻したわけではありません。
映画のクライマックスである燃料集積所は、12月18日にパイパー戦闘団が突入したスタブローの北にあったものをモデルにしているようです。事実では、アメリカ第526機甲歩兵大隊のポール・J・ソリス少佐がパイパー戦闘団の攻撃によりスタブロー撤退後に、ドイツ軍が燃料集積所を狙っていると思い、守備していたベルギー兵の分遣隊に火を付けさせたものです。パイパーはこの集積所に対し一兵も派遣していませんし、もちろんパイパー自身もそんなところで戦死していません。
バルジの戦いのような比較的長期の戦いの場合、有名なエピソードがいくつかあります。そのエピソードもやはりアメリカ映画ということでわざわざ挿入されたり、されなかったりしています。まず一番有名なエピソードとして、包囲された要衛バストーニュ(アメリカ第101空挺師団が守備)に対して行われたドイツ軍の降伏勧告に対してのアメリカ軍の返答があります。これは、ドイツ軍が、長々と降伏勧告を書いてよこしたのに対し、アメリカ第101空挺師団長マッカーリフ准将が返答として一言"Nuts!"と答えたものです。("Nuts"の意味は、英和辞典で是非引いてください。このエピソードは、アメリカの小学校の歴史の教科書にも出ているそうです)この話は映画の中でも突然出てきます。このエピソードはバルジの戦いでおそらく一番有名なエピソードですけど、パイパー戦闘団とは全然関係ないものです。二つ目は、マルメディの大虐殺。これは、アメリカ軍捕虜がSS第1戦車師団によって虐殺されたものです。この話は、戦犯裁判などのとても大きな話になるため詳しくは書きませんが、事実としてはドイツ軍側に公式にそのような命令が出ていた証拠が無いなどの疑問点があり、今となっては偶発的なものなのかどうかはわからなくなっています。(逆にアメリカ軍の一部の部隊で、SS及び降下猟兵は捕虜とせず発見次第射殺せよとの命令をしていた部隊があったのは事実のようです)にもかかわらず映画では、さも一方的に意図的に虐殺されたように描かれています。最後にもう一つ、これもパイパー戦闘団とは関係ないのですが、シュネー・アイフェル高地で南北戦争以来の、そしてヨーロッパにおけるアメリカ軍史上最大の屈辱として、まるまる2個連隊とその付属部隊が降伏し、アメリカ兵約1万名の捕虜とその装備がドイツ軍の手に渡ったというアメリカ軍の敗北があります。さすがにこの話は、映画には出て来ません。
映画の中で、ドイツ軍がアメリカ兵に変装して各種のサボタージュを行ったというのは事実ですが、これは次の「グライフ作戦」を参照してください。
ラスト・シーンでは、昼間(!)にドイツ軍が徒歩で撤退しているところをヘンリー・フォンダが偵察機で見ています。これは全く間抜けなシーンです。完全に連合軍に制空権を奪われていた当時に、昼間にのこのこ歩いていたら連合軍の爆撃で全滅していまいます・・・
(5)グライフ作戦
ヒトラーは、「ラインの守り作戦」が論議されるようになった当初からミューズ川の橋梁の奪取について重要視しており、あらゆる可能性を検討した結果、特殊部隊を編成しその任にあたらせることにした。そして、とある男がヒトラーに直接呼び出された。彼の暗号名は「ゾラー博士」。彼の任務は、アメリカ軍の制服を着て、アメリカ軍の車輌や兵器で装備した部隊を編成し、いくつかのグループにわかれて主部隊の攻撃による敵の混乱に乗じて、退却中の部隊であるかのようにみせかて、ミューズ川への道にかかる橋梁を爆破されることなく確保することであった。この部隊が第150戦車旅団であり、この作戦が「グライフ作戦」であった。この任務の準備のために「ゾラー博士」に無制限の許可が与えられた。
「ゾラー博士」の要請のもとに西部戦線の各部隊から捕獲したアメリカ軍の装備や車輌が集められたが、それらの数は当初の予定を大幅に下回るものであった。その上、作戦遂行上不可欠な語学力を持った志願兵が集まらず、このため第150戦車旅団の編成規模は縮小され、その代わりにアメリカ軍の制服を着てジープで移動し、爆破、虚偽命令、連絡網分断などのテロやサボタージュ活動を行う小人数のコマンド部隊がいくつか編成された。
「ゾラー博士」のもとに集められたアメリカ軍の装備は、第150戦車旅団を編成するにはあまりにも数が少なかった。このため、パンターをM10駆逐戦車に偽装したり、ほとんどの装備予定のドイツ軍車輌に連合軍の白い星マークを付けた。しかしながら、この部隊はどうみてもドイツ軍にしか見えなかった。また、集められたアメリカ製兵器はコマンド部隊に行き渡る分しかなかった。
訓練中の旅団内で、指揮官である「ゾラー博士」の正体がだんだんわかってくると、兵士の間で様々な噂が流れた。「ゾラー博士」は当初、それらの噂で連合軍情報部の注意を引く事を恐れていた。しかし、後には、逆に当初の目的から大きくそれた噂によって、連合軍情報部を混乱させることを狙った。その中には、部隊は戦線に密かに侵入してパリに到達し、パリ市内を行進して連合軍の首脳をまとめて誘拐すると言うものまであった。
「ラインの守り」作戦開始数日前に、SS第I戦車軍団は、その作戦担当地域で「ゾラー博士」率いる部隊が特殊作戦を実行し、その特殊作戦グループは絶対の優先権を与えられ、その部隊の車輌を妨げてはならないとされた。作戦開始の2日前の12月14日、「ゾラー博士」は自分達の特殊部隊の説明を行うためにSS第I戦車軍団司令部に現れた。この「ゾラー博士」こそ、「ヨーロッパで最も危険な男」オットー・スコルツェニーSS中佐その人であった。
第150戦車旅団であるが、作戦開始当初のロスハイム周辺での大渋滞に巻き込まれ、最初の2日間で予定の進発点に到達できなかったことから、スコルツェニーは、この時点で作戦が失敗したと考えた。12月17日、スコルツェニーは第6戦車軍団司令部で、第150戦車旅団を通常の部隊として運用することを提案し承認された。第150戦車旅団は、12月21日、マルメディ攻撃を開始した。スコルツェニーは、12月17日にコマンド部隊から受けた報告を基に作戦計画を立案していたが、すでに強力なアメリカ軍がマルメディに布陣していた。結局、数日続いた戦闘でも遂に第150戦車旅団はマルメディを陥とすことができず、それどころか、スコルツェニー自身、攻撃開始日の12月21日の午後に危うく失明しかけるほどの重傷を負っている。
さて、コマンド部隊の方であるがこちらの方は、テロ、サボータジュ活動自体はさほど効果はなかったが、心理面で多大な成果があったといえる。実はグライフ作戦の存在は、なんと「ラインの守り作戦」開始前日の12月15日に第62国民擲弾兵師団内部で配布されていた書類がアメリカ第7機甲師団の手に落ちており、作戦の意図や目標こそ明らかにはならなかったものの、何らかの偽装作戦が行われることは、連合軍の既知となっていたのであった。そして作戦開始の2日後12月17日にアメリカ軍全体が味方同士疑心暗鬼になる出来事があった。それは、この日にアメリカ軍に捕まえれたドイツ軍のコマンドの一人が、噂の一つであった、スコルツェニーはヨーロッパ連合軍総司令官アイゼンハワー元帥を誘拐するために出てきたという話の裏付けになることを話したのであった。実際、敵の戦線後方にスパイを送り込むことは希有な作戦でもないが、両軍にその名を知られていたスコルツェニーが絡んでいるということもあり、連合軍は緊張したと思われる。このことがあってからアイゼンハワーは司令部内に缶詰状態にされ、アルデンヌ全体でアメリカ軍は誰一人として疑惑を免れなくなった。単に互いを疑い合い行動を制限するだけでなく、ひどいものでは味方を誤射し死亡者までだしたこともあった。一方、コマンド部隊の方は敵の制服を着ているため、捕らえられてスパイと言うことで銃殺された者も少なからずいた。アメリカ軍は疑惑のために、州都の名前、有名女優の結婚相手、大リーグのチーム名など、階級を問わずに質問していた。(ブラッドレー中将も回顧録の中でこのことで閉口した事を述べている)単に答えられるだけでなく、発音がおかしい者も拘束されたりした。また、コマンド部隊が後方に潜り込むまで知らなかったことによって捕まえられたチームもあった。例えば、アメリカ軍はジープに4人以上乗ることはなく(4人以上で乗るのは軍規違反)、3人しか乗らない、とか、アメリカ軍はドイツ軍のようにライトに減光カバー(灯火管制カバー)を付けたりせず、ライトを点ける消すかいずれかしかしないなどであった。この作戦はドイツ軍の正規軍にも少なからず影響を与えている。戦争末期で衣服の質の低下していたドイツ軍の多数の兵士が死んだアメリカ軍兵の暖かい野戦服やオーバーを手当たり次第に着込んで、そのまま捕まりスパイとして処刑されたりしている。
(6)参考文献
「バルジの戦い」上下巻(原題"BATTLE OF THE BULGE THEN AND NOW")
ジャン・ポール・パリュ著 岡部いさく訳 大日本絵画刊
「炎の騎士 ヨーヘン・パイパー戦記」
小林源文作 大日本絵画刊
「W.W.II戦車隊エース」
斎木伸生著 光栄刊
「グラフィック第2次大戦アクション 最後の決闘バルジ作戦」
文林堂刊
「第二次世界大戦 ヨーロッパ戦線ガイド」
青木 茂著 新紀元社刊
「コンバットAtoZシリーズ 図解・ドイツ装甲師団」
高貫布士・上田信著 並木書房刊
「グラフィックアクション ゲルマンの無敵戦士 武装親衛隊の奮戦!」
文林堂刊
[歴史群像]第二次大戦欧州戦史シリーズ
学習研究社